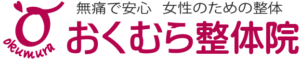リウマチからの贈り物(37) 靴下の繕いものが教えてくれたこと
その他
このブログは、関節リウマチのような「治らない」とされている病気の方々に参考になることがあればと、書いています。また、ご病気でない方でも、病気のとらえ方、医療との付き合い方、代替療法の取り入れ方……など知っていれば、役に立つ情報もお伝えします
靴下の繕いものが教えてくれたこと
私は10年程前から、靴下を重ね履きしています。
重ね履きについて初めて本で読んだとき、靴下を5枚重ねてはく方法が紹介されていました。絹の靴下、綿の靴下、絹の靴下、綿の靴下を順番に重ねてはいて、その上から自分の好きな靴下をはきます。
足を温めるだけではなく、絹が汗や毒素を吸収して、それを綿に吸わせていくという、毒だしの意味もあるそうです。
私も最初は5足はいていましたが、靴下の洗濯が大変なのと、絹の靴下は値段が高く破れやすいため、今は2枚の重ねばきに落ち着きました。
最初にはく靴下は、内側が絹、外側が綿素材でできているものにしています。それを1枚はくだけで、絹、綿を重ねばきしたことになる優れものです。
その上に、季節に応じて綿素材やウール素材の靴下をはいています。
夏も汗を吸い取ってくれ、サラサラしていますし、冷房や床からの冷えから足を守ってくれます。冬はとても暖かく快適です。
数年前、友人の結婚式で、久しぶりにストッキングをはいたとき、足が冷えて冷えて、こんなに違うのか…… と驚いた記憶があります。足元が冷えると、肩に力が入ります。それによって、肩や首のコリ、頭痛の原因にもなります。
内側が絹、外側が綿素材でできている靴下は、絹の靴下よりも丈夫ですが、それでも、アクリルなどの靴下と比べると、破れやすいのです。
リウマチになる前は、靴下に穴があくと、その部分だけ縫い合わせて、なんとか持たせていました。それでも、無理に引っ張って繕っていたため、そのそばから穴があいて…… を繰り返し、結局捨ててしまうこともありました。
リウマチとなり、自宅で過ごす時間が格段と長くなってから、せっかく家にいるのなら、今までよりも生活をもっと丁寧にしてみようと、思いました。
そして、お世話になっている靴下を長持ちさせるために、丁寧に繕ってみたのです。
現在、私は手首に痛みがあり手首を動かしづらいのですが、繕いものをすることで、負担をかけずに手のリハビリができるというメリットもあることに気付きました。
そして、靴下を繕うのにとても便利な道具があります。
「ダーニングマッシュルーム」といいます。
前から持っていたのに全く使っていませんでした。実際に使ってみると、本当に使いやすく繕いものが楽しくなります。木製で手触りもよく、形もとてもかわいらしいです。触ったり見てるだけでも癒されますよ。
この道具は、本来は靴下の穴に糸を縦横に渡して(織物のようにして)塞ぐためのものですが、私は当て布をしてそこにステッチをして塞ぐために使っています。
もう、すでに使っている方もいるかもしれませんが、ご紹介しますね。

次のような穴があいた靴下を裏返して、ダーニングマッシュルームにかぶせ、付属のゴムで靴下を固定します。



穴よりも大きめの当て布を当て、ずれないように待ち針を打ちます。

当て布の周囲に沿って縫います。

靴下を表にし、再度ダーニングマッシュルームにかぶせ、ゴムで固定します。
後は、当て布と靴下がしっかりとくっつき、また穴がふさがるように、自由にステッチをします。ここでは分かりやすいように青糸を使いましたが、目立たない色にしてももちろんいいです。完成です。


何足も、こうやって繕っている内に、繕いものって手のリハビリだけではなく、心にいいなあ、と思い始めました。
自分の体を快適にしてくれていたものに、今まであまり感謝がなかったな、とも感じました。丁寧に感謝を込めて繕うと、靴下がかわいく丈夫に蘇り、また、私の体のためになってくれる。
こんなことを、穴のあいた靴下たちは教えてくれました。
これもリウマチからの贈り物の一つです。
感謝感謝
いつも、最後まで読んで頂き、ありがとうございます。
おくむら整体院 奥村多恵子