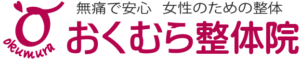リウマチからの贈り物(28) 西式健康法
その他
このブログは、関節リウマチのような「治らない」とされている病気の方々に参考になることがあればと、書いています。また、ご病気でない方でも、病気のとらえ方、医療との付き合い方、代替療法の取り入れ方……など知っていれば、役に立つ情報もお伝えします
明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願い致します。
今年の最初のブログは、私が実践している運動、「西式健康法」をご紹介します。
新型コロナの影響で、自宅で過ごすことが多くなった今、何か継続できる運動をお探しの方にもぴったりです。最初は難しいところもあるかもしれませんが、ポイントを押さえれば、とても簡単にでき全部やっても30分程度です。年齢がいっても継続できますので、習慣にするととてもいいと思います。
西式健康法は、西 勝造先生が1927年に開発した健康法です。16歳の時、医者から20歳まで生きられないと言われ、さまざまな健康法を実行し、やがて健康を取り戻したそうです。その運動を広めたものです。
以前のブログにも書きましたが、玄米菜食で難病の患者さんを治療した甲田光雄先生は、若い頃、医者から見放されたご自身の病気を、玄米菜食と西式健康法で治されました。
そして、「西式健康法」も治療の一環として患者さんに指導されたのです。これらを総称して「西式甲田式療法」と呼びます。
私はリウマチになる少し前から、この健康法を少しずつ始めていました。体を日々整えるにはとてもいい方法だと思い、整体院に来られた患者さんにはセルフエクササイズとして、お伝えしていました。
リウマチと診断されてから、日に2回するようになりました。痛みがあるときは、痛みがでないように適宜変更してやるようにしていました。今は、手首と足の裏以外の痛みがないため、変更なくそのままの運動ができるようになりました。
7月後半~9月後半まで、痛みのために出かけられない日もあり、必要最低の歩行しかできませんでした。それでも、内臓の不調もなく、また足の筋力が極端に落ちることなく、今では通常の生活に戻れています。これもこの運動を継続していたおかげだと思います。
以下にご紹介する全ての運動は背骨や内臓、腸、骨盤、血液の流れを整える作用があります。背骨を整えることで、自律神経のバランスも良くなり内臓や血液の流れなどにも影響するのです。
健康のため日々続けられる運動を探している方、痛みがあって運動不足になっている方、自分を整えるために何か運動を探している方……お試しください。
YouTubeでは、もっと詳しく紹介されていますので、参考にしてください。
1.平床寝台
平らな床に寝ることをさします。
背骨を睡眠中に正しく調整することができます。寝床が硬いことで、皮膚と肝臓に刺激を与えて、皮膚近くの静脈の働きを助け、血液の戻りを活発化させて腎機能を高めます。
私はマットレスをやめて、すのこベッドに薄く硬めのふとん、いわゆる「せんべい布団」を敷きました。床でなくてもこの程度でもいいと思います。今までふかふかのマットレス、布団で寝ていた方は最初は痛く感じますので、少しずつ薄くしてならしていったらいいと思います。
私は、これによって朝起きたときの鈍い腰痛がまったくなくなりました。
2.硬枕(こうちん)を利用する
就寝時に木の硬い枕を使います。

このかまぼこ型の枕は、睡眠中に頚椎(首の骨)の狂いを整えてくれます。
最初は、タオルなどを当てて使ってみてください。こんな硬い枕で寝るなんて!と最初は驚きました。逆に首に悪いのではないとさえ思いましたが、寝起きが爽快になる、と書いてあったので、恐る恐る使ってみました。
初めて使ったときは数分で辛くなり、就寝時には首の下にあった枕が、いつの間にか外れてしまっていました。慣れてくると、この枕の方が楽になります。枕の高さはいくつか選択できます。使う人の薬指の長さに近いものを選んでください。
また、首を伸ばして寝ることになるため、年齢とともに出てくる「首の横じわ」が出にくくなる方もいるそうです。
3.毛管運動:2分程度、朝晩1回ずつ
手足などの末端では古い血液がうっ血、停滞しがちです。この運動は血液循環を良くします。冷えやむくみにも効きます。
最初は1分でも辛くなります。できる範囲で少しずつ時間をのばしていってください。必ずできるようになります。座りっぱなし、立ちっぱなしなどで足がむくんだときなどにすると、効果が分かりやすいです。

1.硬枕をし、平な床に横になり手と足を天井の方に伸ばす。
*硬枕がない場合は、バスタオルを硬く巻いてくびの下に入れる。
2.手指はすべてくっつける。足裏が床面と水平になるようにする(足首を90 度で固定)。
3.手足を前後に細かくけいれんさせるように震わせる。肩、太ももの付け根から震わせるようにすること。
*いろいろな方向に震わせるのではなく、必ず、前後に震わせる。足を震わせることが難しいときは、足の角度は固定して天井をける気持ちでするとやりやすい。
4.合掌合蹠(がっしょうがっせき)運動:100回(1往復を1回とする)、朝晩1回ずつ
左右の脚長差を調整し、下半身の血流を高める運動です。骨盤内臓器の症状を改善するのにも役立ちます。この運動は「安産の秘法」とも呼ばれ、流産・早産を経験した人や、生理痛のある人にも効果的だとされています。

1.仰向けになって胸の前で合掌する。足の裏どうしをぴったりと合わせる。
2.両手を上に伸ばすと同時に、足も伸ばす。このとき、両方の足の裏はくっつけたままで行う。
3.往復で100回終了後、手足は縮めたままで2~3分停止する。
*足がこすれで痛い場合は、厚めの靴下をはいたり、タオルなどを敷いて運動する。
5.膝立て金魚運動:100往復、朝晩1回ずつ
背骨の左右の違い調整して、腸内の内容物(便)を均等にして便通を促します。腰痛予防にもなります。
「金魚運動」として紹介されているものよりも、「膝立て金魚運動」の方が行いやすく、腰への負担が少ないと私は思いますので、こちらを紹介しました。

1.後頭部で両手をしっかり組み、胸をそらす。
2.踵をできるだけお尻によせる。
3.両膝が離れないように、膝を左右交互にゆっくり倒し床につける。このとき、胸はそらしたままで。
6.背腹(はいふく)運動:10分間で500回程度、朝晩1回ずつ
この運動が一番大切な運動と言われています。背骨を振り子のように左右に揺らしながら、おなかをふくらませたりへこませたりする運動です。
背骨を左右に振ることで背骨のゆがみを整え、交感神経を刺激します。さらに、おなかの運動をすることで、副交感神経を刺激します。交感神経、副交感神経両方の力を等しく発揮させるということです。
この運動による交感神経、副交感神経の状態は潜在意識に植え付けられ、自己暗示が聞く状態になるそうです。つまり「自分が願うことをこの運動時に描いていけば、思いも実現しやすくなる」と甲田先生は言われています。

1.正座、または椅子に座る。手は膝に軽くおいて固定する。
2. 背骨を振り子のように左右に揺らしながら、おなかを膨らませたり、へこませたりする。体が左右に傾いたときに、おなかを押し出し、体が真ん中にきたときに引っ込める。
*メトロノームアプリ(50~55回/分程度)に合わせるやりやすい。
●参考文献
・「マンガでわかる 西式甲田式療法 甲田光雄、赤池キョウコ マキノ出版
・「断食の教科書」森美智代 ヒカルランド
いつも、最後まで読んで頂き、ありがとうございます。
おくむら整体院 奥村多恵子